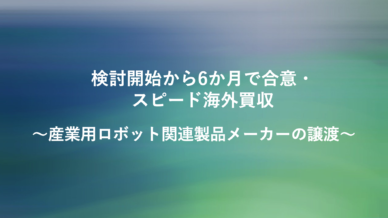 事例
事例 検討開始から6か月で合意・スピード海外買収 〜産業用ロボット関連製品メーカーの譲渡〜
対象企業事業内容産業用ロボット関連製品の製造および販売所在地EU売上高約18億円従業員約60名譲渡理由相乗効果のある企業への傘下入り 譲受企業事業内容産業用ロボット関連製品の製造および販売所在地日本売...
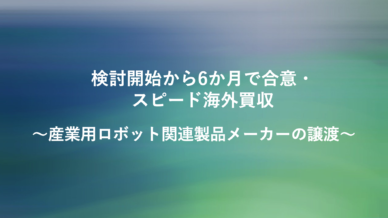 事例
事例  海外進出
海外進出  海外進出
海外進出  ホワイトレポート
ホワイトレポート  ホワイトレポート
ホワイトレポート 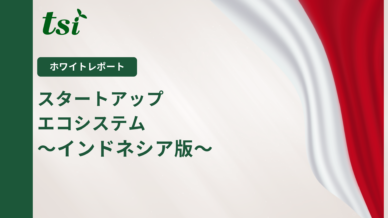 ホワイトレポート
ホワイトレポート  海外進出
海外進出  海外進出
海外進出  海外進出
海外進出  M&A
M&A  M&A
M&A  M&A
M&A 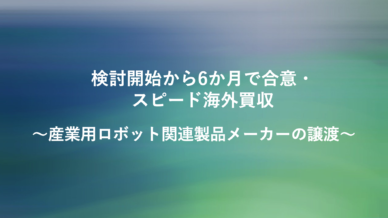 事例
事例 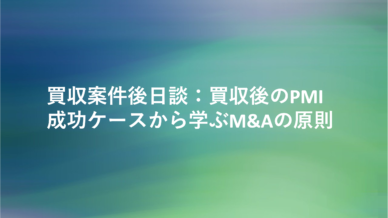 事例
事例 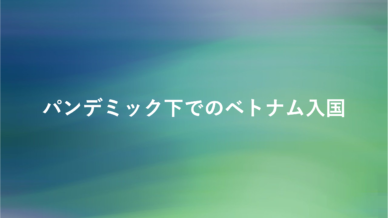 事例
事例